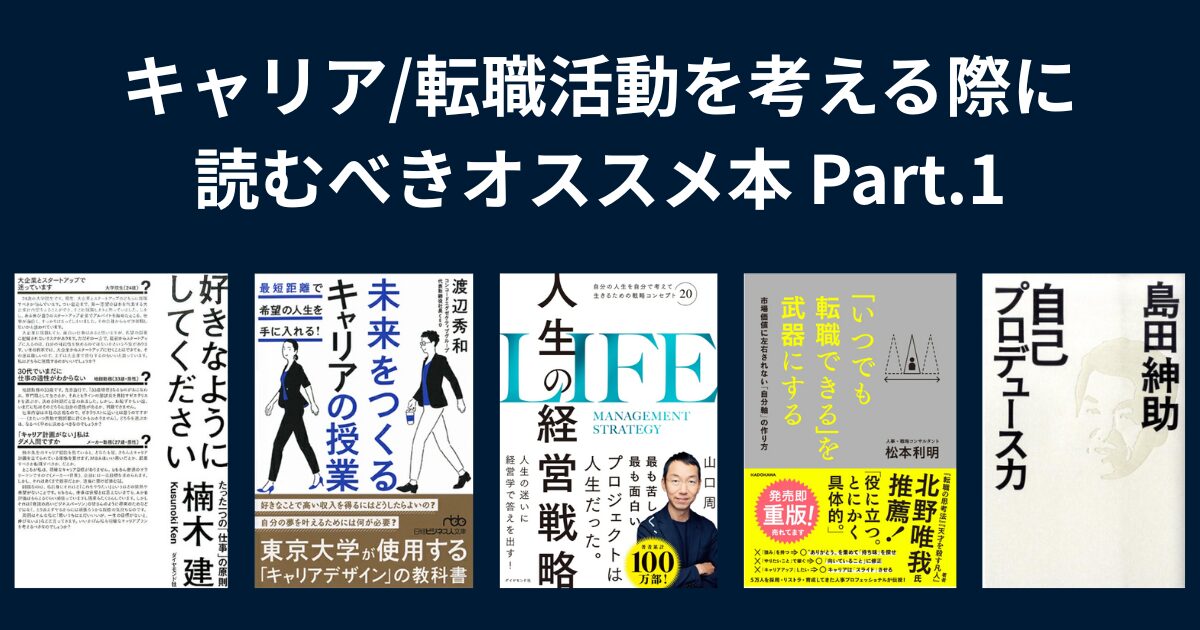面接は事前準備がほぼすべてを決める世界です。
ここでの準備とは、単に素晴らしい想定問答を作り上げることだけでなく、実際の受け答え・デリバリまで含んだ準備を指します。
「面接は見た目が9割」などとよく言われますよね。
メラビアンの法則によると、人が受け取る印象は、
- 言語情報(Verbal):7%
- 聴覚情報(Vocal):38%
- 視覚情報(Visual):55%
という比率で影響すると言われています。
定量値の正確性はさておき、これはノンバーバルのコミュニケーションが非常に重要だということを示唆しています。
なので、「何を言うか」だけでなく「どう見せるか」。
面接での回答そのものの内容に加えて、デリバリのトレーニングも大切になってきます。
とはいえ、見せ方を整えるには、土台となる想定問答への自信・納得感が不可欠です。
自分の中で腹落ちした想定問答を作り込むことが、結果的に質の高い印象に繋がります。
私はこれまで、50社以上・100回以上の面接を受けてきました。
中身は全く大したことないのですが、面接突破力を磨き上げることで希望のキャリアを掴み取ってきたと振り返っています。
本記事では、面接対策・逆質問のポイントと、よく聞かれる質問について、個人的な経験に基づき解説していきます!
面接における質問対策
①訴求ポイントを明確化する
すべての問いに対して、結論ファーストで端的に回答できるように準備します。
当たり障りのない、なんとなく置きに行ってしまっている回答は徹底して排除し、訴求ポイント(言いたいこと)をスパッと言い切れるようにする必要があります。
そのためには、大きく2つのアプローチがあります。
A. 訴求ポイントを具体理由・エピソードで磨き込み
- 自分の中で、「この質問にはこう答えたい」という訴求ポイントを仮置きする
- 訴求ポイントに対して、それをサポートする具体的な理由やエピソードを整理する
- 具体的な理由・エピソードを踏まえて、仮置きした訴求ポイントをブラッシュアップする
B. メッセージ自体が面白いものになっているかチェック
訴求ポイントが誰にでも当てはまりそうな話だと、面接官の心を動かせません。
多くの候補者を見ている面接官にとっては、「またこのパターンね」となります。
一方で、自分の回答の良し悪しを自力で判断するのは難しいです。
エージェントや信頼できる人にチェックしてもらい、「ふわっとしてる部分」や「説得力に欠けるポイント」を一つずつ潰していく作業が必要です。
②引き出しの構造化で、対応力をつける
質問に対する想定回答はすべて構造化し、常に結論ファーストで引き出せるように整理しておくことです。
基本的に面接では、できる限り端的な回答がベターです。
ただ、面接に駆り出される面接官は必ずしも面接のプロではなく、素人面接官に当たるケースも少なくありません。
そうした場合、結論だけを述べても深掘ってくれず、「So what?」という雰囲気になります。
その時は、結論だけではなく、具体的な理由やエピソードを小出しにしながら、面接の流れをグリップしていく必要があります。
その場の空気を読んで、回答を適切な粒度感に柔軟に調節できるかが鍵です。
ただ、行きたい企業の面接、緊張でそこまで余裕はないですよね。
そのため、ガチゴチ状態でもクリアに受け答えできるよう、あらかじめ引き出しを構造化して整理しておくことが最大の備えになります。
イメージはこんな感じ↓
• 私の強みはXXです!
– 強みを裏付けるエピソード1
– 強みを裏付けるエピソード2
• 私は入社後XXをしたいです!
– XXをしたい理由1
– XXをしたい理由2
③自然に話せる言葉に落とし込む
①②で想定問答集を作りこんだ後は、それを面接の場でスムーズに使いこなせるように仕上げていくフェーズです。
テキスト上は正確でも、実際に自分が話しにくい表現になっていると逆効果です。
奇をてらった表現は一切そぎ落とし、自分にとってのナチュラルな話し言葉に変換していく作業です。
意外と見落とされがちですが、面接の完成度を左右する重要な工程だと思っています。
声に出して話す練習を繰り返しながら、自分の口に馴染む言葉に落とし込んでいきましょう!
面接本番は“準備の記憶”を捨てよう ー その場のアレンジ力がすべて
上記の3つはいずれも面接前の準備内容です!
基本的に対策すればするほど合格確度は上がっていきますが、面接本番のデリバリにおいては注意が必要です。
準備内容の吐き出しにフォーカスしてしまうと、暗記内容を思い出すことにエネルギーを使ってしまったり、そこに引っ張られて余計なことまで話しすぎるリスクがあります。
そうなると、面接官の微妙な反応や質問の意図、それに対してどのような粒度での回答が必要か?といった意識が希薄になり、不合格の確率が一気に高まります。
面接は面接官の評価で決まる属人性の高いプロセスです。
「自分の経験の素晴らしさを伝えること」ではなく、自分の経験の素晴らしさを「面接官が理解すること」が必要です。
そのため、逆説的ですが、面接本番ではいままで準備してきたことは全て忘れるべしです。
文脈的に何を聞かれているか?に意識を全集中させ、それに対してドンピシャの回答をその場でカスタマイズすることが重要だと思っています。
こうした準備を一人でやり切るには限界があります。
自分的には自信作であっても、客観的に内定レベルにミートしていなければ、面接を受ける前にドボンです。
そのため、ここはエージェントを積極的に利用しましょう。
特に親身になって考えてくれる担当者を探すことが大切です。
想定問答のブラッシュアップから模擬面接まで、あらゆる対策を無料でやってくれるので、使わない手はないです。
もし自分に合ったエージェントにまだ巡り合えていない方は以下を参照しながら、ぜひ使ってみてください!


転職面接でよく聞かれる質問
自分が面接対策する中で主に準備していた質問事項をリストアップしました!
8-9割の質問に対応できていると思います。
たまに想定外の質問も来ますが、8-9割ですでに合否は決まっているので、それほど神経質になる必要はありません(もし来たら、その場で最大出力の瞬発力を発揮し、打ち返すほかないです)
すでに選考対策を進められている方も、抜け漏れがなさそうか再確認する材料として使っていただければと思います!
経歴関連
- 自己紹介してください
- 現職の業務
- どのような業務に従事しているか
- 業務の規模や組織の体制は
- その中でのあなたの役割は
- 現職の成果
- 最大の成果は何か
- なぜそれに取り組んだか
- どういう目標を設定し、どのような体制で取り組んだか
- いつ、どの程度の期間で取り組んだか
- どういう課題・困難があったか
- 課題に対して、どのような打ち手を講じたか
- それによって得られた成果は
- その経験での学びと今後への活かし方は
- 仮に当時に戻ったとして、改善すべきと思うことは
- 失敗/挫折経験
- どのような失敗/挫折経験があったか
- それらに対して、どのように対応/克服したか
- 現職の評価
- 現職における評価内容は
- どのような評価体系となっており、自分はどういう位置づけか
- 最後に言いたいことは(面接ラストの一言)
志望動機関連
- 志望動機を教えて(Why 業界・企業・部門)
- 転職を考えたきっかけは何か
- 現職に入社を決めた理由は何か
- 入社後やりたいことは何か
- Fit & Gap
- やりたいことを実現するために、今の自分ができること・できないことは
- できないことをどうキャッチアップしているか/していくつもりか
- XX年卒(自分の新卒入社年度)の社員と比較した際のあなたの優位性は
- 今後のキャリアプランについて、どう考えているか
- 志望業界/企業のイメージ
- 現職と志望業界/企業の違いは何だと思うか
- どのような業務イメージを持っているか
- 希望業務に就けない可能性があるが問題ないか
その他/パーソナリティ関連
- 強み・弱み
- 強み・弱みは(ハードスキル、ソフトスキルそれぞれ)
- 強みを活かして、どのように貢献できると考えているか
- 弱みをどのように解消していこうとしているか
- リーダーシップ経験
- 他人をリードした経験を教えて
- 自分の役割や義務を超えて、リーダーシップを発揮した経験は
- マネジメント経験
- マネジメント経験はあるか
- チーム内で目的達成を阻害するようなコンフリクトに直面した経験は
- ステイクホルダーとの意見の対立が起きたときにどう対処するか
- パーソナリティ
- 周囲からどんな人だと言われるか
- 仕事/人生において、大切にしている価値観は何か
- モチベーションの源泉は何か
- ストレス耐性はあるか
- 尊敬する人はどんな人か、苦手な人はどんな人か
- ケイパビリティ
- 駐在・留学経験はあるか
- 英語は使えるか(英語を使った業務経験はあるか)
- パワーポイントやエクセルは使えるか(業務での使用経験はどの程度か)
- ニュース/本
- 最近気になったニュースを教えて
- 最近読んだ本の中で面白かったのは(自分の趣味が読書であったため)
- 業界課題・今後の展望
- 自分の所属・応募先の業界・企業の課題は何だと思うか
- 今後どのような成長方向性が考えられるか
逆質問で押さえるべきポイント
面接最後には、ほぼ確実に逆質問タイムが設定されると思います。
数々の逆質問を乗り切る中で「これは刺さってるな」と意識していたポイントについて、紹介しておきます!
①面接の場で出てきたフレッシュなネタを拾う
できる限り、面接で出てきた話題を引用しながら、逆質問することです。
「先ほどお話しされていたXXについて、もう少し詳しくお伺いしてもよいでしょうか?」といった具合です。
事前に用意した質問は、他の候補者も聞いている可能性が高いですが、その場の話題を拾えば、自分だけの文脈に即した質問になり、印象に残りやすいです。
「お、この人、話の本質を掴んでるな」という評価になると思ってます。
その場の内容なので自然で流れがよく、「会話している感」が強まるためオススメです!
②相手に語らせる質問をする
といっても、毎度その場で質問が思い浮かぶとは限らないです。
その場合は、とにかく相手に気持ちよく話してもらう質問を投げかけることです。
というのも、面接のゴールは相手にポジティブな印象を残すことであり、相手の心を動かせるかで決まるためです。
基本的に人は自分の経験・思いを語るときに気分が乗るため、そうした話を引き出す質問が効果的です。
そのためには、事前に面接官側の情報をインプットできるかが鍵です。
エージェントや社員ヒアリングを通じて、どんな面接官かを確認できるとベストです。
特に面接終盤に出てくるような偉い人であれば、公開情報ベースで過去の経歴やコメントを拾えることが多いです。
そこに根差した質問を繰り出し、ヨイショに徹して、武勇伝を語らせることができれば逆質問パートはクリアです!
③仮説を持った質問をする
自分の考えを前置きしてから質問すると、“深く考えている人”っぽく映ります。
仮説は外れていてもOK、むしろそのズレを起点に議論が生まれることもあります。
逆質問を起点に面接官と対等な議論に持ち込むことも、成功パターンの一つだと思います!
例えば、「最近の貴社の注力領域を見ると、デジタル案件が増えている印象を受けました。従来の経営戦略とは違ったスキルセットが求められるのではと想像したのですが、実際にどうでしょうか?」といったイメージです。
仮説ベースの質問は「攻め」の一手です。
“企業を見る”ではなく、“企業に見られる”ための時間に置き換わります。
少しでも合格確度を上げるべく、最後の最後まで粘って、できる限り筋の良い仮説を差し込めるとベストです!
まとめ
ひとつひとつの問いに向き合うことは転職活動を超えて、これまでの経験の振り返りや自分の価値観に向き合う貴重な時間になると思います。
ぜひ本記事の質問に向き合って考えてみていただけると嬉しいです。
ただ、転職活動自体にストレスが伴うのも事実ですよね、私も本業との両立には非常に苦労しました。
そうした時は、インプットの時間も取りながら、カジュアルに自己分析を進めていくこともオススメです!
「自分はどうありたいのか」、「自分が本当にやりたいことは何なのか」といったことは、他者の考え方を鏡にしながら考えてみると、思わぬ発見があったりします。
こちらでおすすめ本を紹介してるので、ぜひ参考にしてみてください!